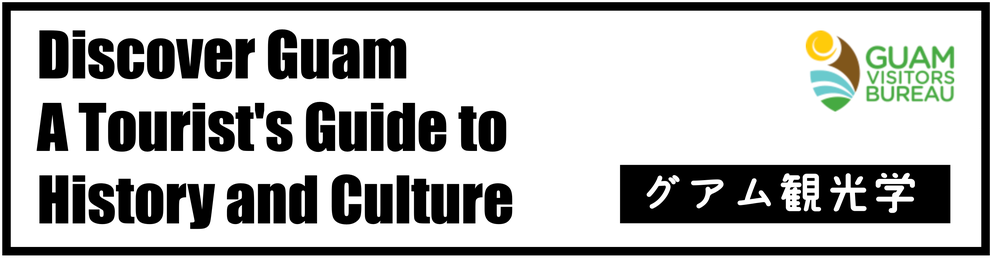▪️変遷と現代的意義
日本の高等学校教育における海外修学旅行は、長年にわたり生徒の成長に多大な貢献をしてきました。その役割は時代とともに進化し現代のグローバル社会においてその教育的意義は一層高まっています。
●海外修学旅行の歴史的背景と導入経緯
日本の修学旅行は単なる知識の獲得に留まらず実地経験や実践的なスキルの習得に重要な役割を果たしてきました。その起源は古く、日本初の海外修学旅行は1896年に長崎県立長崎商業学校(現在の長崎市立長崎商業高等学校)が上海へ敢行したと記録されています。これは明治時代における国際化への意識の高まりを反映したものでした。
戦後、海外への修学旅行が本格的に再開されたのは1972年で宮崎の高校が韓国を訪問したのがその最初とされています。その後、1978年には福岡の県立高校が公立学校として初めて飛行機を利用した記録があり新幹線(1964年開通)や航空機の普及とともに、海外修学旅行は徐々にその裾野を広げていきました。
●学習指導要領における位置づけと教育的意義の再確認
文部科学省の学習指導要領において、修学旅行は「平素と異なる生活環境にあって見聞を広め、自然や文化などに親しむとともに集団生活の在り方や公衆道徳などについての望ましい体験を積むことができるような活動」と明確に位置づけられています。この定義は教室での学習だけでは得られない実践的な知識や経験、集団行動における規律や公共マナーの習得を重視していることを示しています。
特に、新型コロナウイルス感染症の世界的拡大を経て文部科学省は「生きる力」をキーワードに高校生に広い視野と深い考察をもたらす海外教育旅行の実施を強く推奨しています。専門家も修学旅行は単なる観光ではなく「学びの集大成を図る機会」であると強調しており、教育活動の一環として人間関係形成能力、社会参画意識、自己実現といった多岐にわたる資質・能力の育成に貢献すると考えられています。
●海外修学旅行の目的の進化:経験から意図的な学習へ
海外修学旅行の目的はその歴史の中で大きく進化してきました。初期の段階では知識の獲得に加え実地での経験や実践的なスキルの習得が重視されていました。これは、広範な「経験」を通じて生徒の視野を広げることに主眼が置かれていたことを示唆します。
文部科学省の学習指導要領では、その目的が「見聞を広め、自然や文化などに親しむとともに、集団生活の在り方や公衆道徳などについての望ましい体験を積むこと」と具体化されました。ここでも「体験」が中心ですがその内容がより詳細に定義されています。
近年、この目的はさらに深化し修学旅行が「学びの集大成を図る機会」であり「探究的な学習の機会にしたいというニーズが高まっている」と専門家によって指摘されています。これは、単なる体験に留まらず生徒個々の深い学びや具体的な資質・能力の育成を明確に目指す必要性が認識されていることを示しています。この変化は新学習指導要領で新設された「総合的な探究の時間」との連携を強く意識していることからも裏付けられます。
この一連の変遷は海外修学旅行の目的が一般的な異文化接触や集団行動の経験からより構造化され、生徒の内面に深く作用する意図的な学習へと移行していることを意味します。旅行は「手段」であり、その先に明確な「学習目標」が設定されるようになったのです。このような変化は高額な費用を伴う海外修学旅行の費用対効果を最大化し単なる観光では得られない価値を創出するための必然的な方向性であると考えられます。
▪️果たしてきた役割
海外修学旅行は日本の高等学校教育において生徒の多面的な成長を促す重要な役割を担ってきました。その教育効果は知識の習得に留まらず人間性や社会性の醸成にまで及びます。
●知見の拡大と異文化理解の促進
修学旅行は生徒が普段とは異なる環境に身を置き、その地の自然や文化に直接触れることで知見を大きく広げる機会を提供します。異文化交流を通じて多様な価値観を尊重する姿勢や国際的な視野を養うことが期待されています。
現地の学校訪問やホームステイといった直接的な交流は、生徒が異文化に触れ、コミュニケーションを図る中で、国際社会を担うグローバルな視点を養う上で極めて有効です。
●集団生活と公共マナーの習得、人間関係形成能力の育成
数日間にわたる集団生活を送る修学旅行は、学校以外の場での集団生活のルールや公共マナーを学ぶ貴重な機会となります。飛行機や新幹線といった公共交通機関の利用、ホテルなどの宿泊施設での外泊は、生徒が社会に出た際に役立つ実践的なマナーを身につける上で、かけがえのない経験を提供します。
この期間中、生徒は集団の中での自身の行動を振り返り、他者のペースに合わせ気持ちに配慮するといった他者への思いやりを育むことができます。共に過ごす時間が長いため、友人との関わり合いを深め、協力し合う中で、より良い人間関係を形成する能力が育成されます。
●語学力向上とグローバルキャリア意識の醸成
海外での修学旅行は、生徒が自身の語学力を実際に試す機会を提供し、その重要性を肌で感じることができます。重要なのは、語学学習がそれ自体を目的とするのではなく、何かを達成するための「手段」であることを現地での経験や多様な交流を通じて実感することです。
例えば、現地でのインタビューやプレゼンテーションといった目的を持った言語使用の機会はより効果的な学習に繋がります。実際に、海外教育旅行後には英語検定試験の受験者数や海外大学進学希望者が増加するなど、目に見える形で生徒の変化が実感されています。このような経験は英語学習を将来のキャリアや進学に結びつける意識を引き出し、グローバル意識の醸成に大きく貢献します。
●社会課題への探究と「原体験」を通じた自己成長
海外修学旅行は環境問題や過疎といった社会課題を現地で探究し、その解決策を考える力を育む場となり得ます。現地の専門家や起業家との対話は生徒の学びを深め、次世代のリーダーとしての視点や起業家精神を養う貴重な機会を提供します。
さらに、これらの経験は生徒が社会課題を「自分ごと」として捉える力を育み、多様性の中で協働・共創することで社会とのつながりを実感し、主体性を養う「人生の駆動力となる“原体験”」を提供します。ウェルビーイングと自己成長の観点からは自己理解を深め、自己肯定感を高め、困難を乗り越える力を培う機会も提供されます。
●原体験がもたらす変革的学習の触媒としての役割
海外修学旅行は生徒の人生において「駆動力となる“原体験”」を提供できる点で他の学習機会とは一線を画します。これは、単に「経験する」ことや「見聞を広める」という初期の目的を超え、より深いレベルでの教育効果を示唆しています。「原体験」は生徒が「社会課題に対する当事者意識」を芽生えさせ、自己のあり方を見直すきっかけとなり、「次世代リーダーの育成」に繋がるとされています。これは、受動的な学習ではなく、生徒の内面に深く作用し行動変容を促す能動的な学習体験であることを意味します。
海外修学旅行の真の価値は、単なる知識の獲得やスキル習得に留まらず生徒の価値観や人生観に影響を与えるような「原体験」を提供できる点にあります。この「原体験」は生徒の主体性や問題解決能力、グローバルリーダーシップの育成に不可欠な触媒となり、その後の学習意欲やキャリア形成にも長期的な影響を与えると考えられます。したがって、プログラム設計においては単なる観光地巡りではなく、生徒が深く関わり、内省し、行動する機会を意図的に組み込むことが重要です。
●語学学習の目的:手段としての言語の習得
海外修学旅行の教育効果として「語学力向上」は広く認識されています。しかし、その本質は単なる語学力の習得に留まりません。現地での経験や多様な交流を通じて、語学は日本でも学べますが、それ自体が目的ではなく、何かを達成するための手段であることを実感することが大切です。
海外修学旅行における語学学習の価値は、単に教室で文法や単語を学ぶこととは異なり、生きたコミュニケーションの場で言語を「道具」として使う経験を通じてその実用性と重要性を深く理解させる点にあります。これにより、生徒は言語学習への内発的なモチベーションを高め、将来的なキャリアや進学に繋がる意識を醸成することができます。この理解は、単なる語学研修に終わらない、より実践的で目的志向の語学プログラムの必要性を示唆しています。
▪️円安時代における課題
現在の日本の高等学校における海外修学旅行は、記録的な円安とそれに伴う物価高騰、さらにはコロナ禍からの回復期における新たな旅行環境の変化という、複数の課題に直面しています。これらの課題は、海外修学旅行の実施そのものに大きな影響を与え、教育機会の不平等を招く可能性も指摘されています。
●記録的な円安と物価高騰による旅行費用の増大
記録的な円安は学校の教育現場にも直接的な影響を及ぼしています。費用高騰の背景には円安だけでなく、コロナ禍を経て世界中のホテルが値上げしていることも挙げられています。
海外修学旅行の場合、渡航費や滞在費などへの円安の影響は極めて大きく学校の自助努力だけでは対応が困難な状況が多く見られます。国内においても、ホテル料金の高騰は修学旅行の費用を押し上げています。東京都内のホテル平均客室単価は、2020年1月の約10,000円から2024年12月には約20,000円へとほぼ倍増しており、これは修学旅行の予算設定に大きな影響を与えています。
●安全管理・危機管理体制の継続的な強化の必要性
海外渡航においては日本とは異なる危機管理および健康管理が不可欠であり、事前の情報収集と準備が極めて重要です。外務省が提供する「たびレジ」への登録や海外旅行保険への加入は必須とされており、現地の治安状況、テロ情勢、社会情勢、犯罪の傾向・手口などの最新情報を常に収集することが推奨されています。
●学生の意識と参加障壁
現役高校生を対象としたコロナ災後の調査では約7割が海外旅行に行った経験がなく、パスポート所持率も36.6%に留まっていました。
一方で、約8割の高校生が海外旅行に「興味がある」と回答しており、その理由として「英語を話したい」「異文化に触れたい」「海外の食文化に興味がある」などが挙げられています。しかし、海外旅行に興味がない理由としては、「治安の問題」「言語の壁」「物価が高い」が上位に挙げられており、経済的負担だけでなく、心理的・実用的な障壁も大きいことが示されています。
▪️教育内容の深化と多様化
円安時代における海外修学旅行の課題を克服し、その教育的価値を最大化するためには、多角的な視点からの戦略的な取り組みが不可欠です。
●「学びの集大成」としての探究学習・問題解決型学習への転換
海外修学旅行は単なる観光ではなく、新学習指導要領で重視される「総合的な探究の時間」と連携、「学びの集大成」の場と位置づけるべきです。生徒自身が事前に探究テーマを設定し、現地でインタビューを行うなど目的を持った言語使用の機会を提供することでより効果的な学習が可能です。現地での学びを深めるためには単なる見学に終わらせず、生徒が設定した課題に対して実際にアクションを起こし、その結果を検証する機会を設けることが重要です。
●SDGs(持続可能な開発目標)との連携による地球規模課題への意識向上
環境問題や過疎などの社会課題を現地で探究し、解決策を考える力を育むプログラムを積極的に導入すべきです。観光庁は、SDGsなどの国際的な潮流を盛り込んだ教育的価値の高い海外教育旅行プログラムの企画案を募集し、開発費を支援しています。事前学習としてSDGsに関する社会問題をリサーチし、現地渡航前にオンラインで現地の学生と繋がることで研修目標を明確化し、学びを深めることができます。
●現地交流を通じた多文化共生とグローバルリーダーシップの育成
現地の学生や地域の人々との協働を通じて、コミュニケーション能力や異文化適応力を高めることを目指すべきです。対話や議論で自分とは異なる考え方に触れることで視野を広げ、多角的に物事を考える力を身に付け、社会生活における人間関係形成能力を築くことが重要です。また、現地の専門家や起業家との対話を通じて学びを深め、次世代のリーダーとしての視点や起業家精神を養う機会を提供することも考えられます。
●オンライン交流の積極的活用と事前・事後学習の強化
コロナ禍において、海外修学旅行が中止される中で、オンライン国際交流の事例が増加しました。オンライン交流は渡航前の生徒の言語への不安を軽減し、現地での活動目標を明確にするための事前学習として非常に有効です。オンラインと実地を組み合わせたハイブリッド型のプログラムは、費用抑制と教育効果の最大化を両立する可能性を秘めています。
▪️未来の展望
今後どのような価値を創出し、持続可能な形で実施していくべきかについて考えます。
●「学びの集大成」としての海外修学旅行の再定義
海外修学旅行は、単なる観光旅行ではなく、生徒の「生きる力」を育み、広い視野と深い考察をもたらす「学びの集大成」としての役割を再定義すべきです。探究学習、SDGsとの連携、現地での社会課題解決への取り組み、異文化交流を通じたグローバルリーダーシップの育成など、より目的志向的で能動的な学習体験を核とすることで、その教育的価値を最大化します。これにより、高額な費用を伴う海外渡航が、生徒の将来にわたる成長に不可欠な投資であるという認識を社会全体で共有することが可能になります。
●未来を拓く海外修学旅行の展望
文部科学省が2033年までに日本人学生の海外派遣数を50万人にするという野心的な目標を掲げていることは、日本の将来におけるグローバル人材育成の重要性を示しています。この目標達成のためには、「早期からの留学への意識形成」が重要な課題として認識されており 、高校生段階での国際経験がその基盤を築く上で不可欠です。
海外修学旅行は、長期留学とは異なるものの、「海外に飛び出し、日本では得がたい様々な経験を積み、多様な価値観を持つ世界中の人々との交流により、異文化理解の促進、アイデンティティの確立、国際的素養の醸成等、グローバル人材の育成に寄与」すると明確に位置づけられています。
しかし、現在の記録的な円安や物価高騰、人手不足といった課題は海外修学旅行の実施を阻害し、結果として国家目標の達成にも影響を与えかねません。この状況は海外修学旅行が単なる学校行事の枠を超え、日本の将来を担うグローバル人材育成という国家戦略の中核をなす要素として捉えられるべきであることを示唆しています。
海外修学旅行の持続的な実施と質の向上は、教育現場だけの問題ではなく、政府、産業界、地域社会が一体となって取り組むべき国家的な投資と位置づける必要があります。
\ 海外修学旅行先としてのグアムに関するレポート /